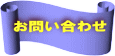上尾観光協会認定ボランティアガイド団体
あげおアッピーガイドの会

トピックスtopics
1/25(金)二ツ宮いきいきクラブ13名の皆様に、駅西コースをご案内しました。
冬晴れの温暖な日和の中で、壱丁目の村社の「愛宕神社」では、神社でのお参りの仕方から始まり、江戸時代中期建築の上尾市指定文化財「見世棚造り本殿」、ご神体は古剣である事のなど説明しました。「十連寺」では、1613年10月、徳川家康が立ち寄り「干菜山光明院十連寺」の名称を付けた事、徳川家家紋「三つ葉葵」印字許可。「慶安の禁札」、「徳本行者念仏塔」、「柴田七九郎父子の墓」が、何れも上尾市指定文化財であることの説明を、観光客は熱心に聞かれていました。
「川の大じめ」は、江戸時代からの厄病が村に入らないようにする「フセギ」と呼ばれ毎年5月15日に川村の入口に「川の大じめ」のしめ縄を張るのでした。これは、上尾市指定無形民俗文化財となっています。
「春日神社」では、明治41年付近の芝宮社、春日社、氷川社の3社が合併し、本殿は昭和18年に造られました。大山灯籠の行事が行なわれるなど、祭神、祭りについて、詳細にガイドしました。
「葬頭河奪衣婆堂」の住宅に取り囲まれた小さな堂の中にある像を見ながら、厄除けと子供のみみだれ・咳止めの江戸時代の民間信仰であり、現在も地域の人達が詣でていると説明されると、特に女性の観光客が熱心に見入っていました。
「柏座2丁目の庚申塔」では、市内にある142個の庚申塔は、建立人名が殆どの塔が男性であるのに、この塔は全員女性名であることが珍しい事と、庚申塔信仰の歴史、意味等を詳しく説明しました。
「谷津観音堂」では、昔は真言宗の福壽山皆応寺と言う日乗院の末寺で、明治五年廃寺となつたが、地元の人が復興し現在に至り、本尊は木彫りの十一面観音立像で、十二年に一回ご開帳される。毎月十日が縁日。院内にある馬頭観音は、明治21年に川越からの二頭立ての馬車が、谷津踏切で汽車に引かれ死亡したのを、上尾町の人が哀れみ供養していると、ガイドしました。
(文:杉山) (写真:小島)
(ガイド・サポート:小島、杉山、峰澤)
 上尾駅でのコース概要紹介 |
 愛宕神社のガイド風景 |
 十連寺のガイド風景 |
 川の大じめのガイド風景 |
 春日神社のガイド風景 |
 谷津観音堂のガイド風景 |