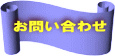上尾市観光協会認定ボランティアガイド団体
あげおアッピーガイドの会

原市(西)コースharaichi west tour COURSE
コースマップ

観光ポイントの説明 →イベント情報(原市西地区)
<推奨コース>| 起点 ニューシャトル原市駅 | |
 |
ニューシャトル原市駅です。売店があります。 原市の語源は、古くは吉野領「原村」に属し、地内の通り(県道大宮菖蒲線)に市が立った事により、町並みが形成され、この地名「原市村→原市町」が誕生した。明治の初期ごろは、人口も町並み上尾宿をはるかに上回り、当時の市場町原市の盛況ぶりがうかがえる。 |
| ① 相頓寺 | |
 |
永徳2年(1382)創建と伝えられる浄土宗の寺。本尊の阿弥陀如来、相頓寺三仏、板石塔婆など、市指定文化財も多く、特に朱色の鐘楼門はとても美しいです。 →相頓寺補足説明 |
| ② 妙厳寺 | |
 |
妙厳寺は曹洞宗の寺院で、延徳元年(1489)に創設されました。妙厳寺には近世初めに原市の領主であった西尾氏の墓(市指定文化財)があります。西尾氏の墓域の隣には代々名主を勤めた矢部家の墓があり、幕末から明治初期に私塾を開いた伊藤由哉(ユウサイ)碑と墓(市指定文化財)も所在し、見るべきものの多い寺院です。 |
| ③ 原市氷川神社 | |
 |
近世における市場集落の面影を残す原市には、上町・中町・下町・上新町・下新町の五つの町内がある。当社は、その内の上町・中町・上新町の三町内の守り神として祀られてきた神社である。その境内はかつて道の両側に市の立った原市の本通りのすぐ脇にあり、現在は樹木がほとんどないが、昭和五十年台の中ごろまでは参道の敷石を挟むように木々が茂っていた。当社の創建についての経緯は不明であるが、『風土記稿』原市村の項に「氷川社 本地仏正観音の像を安ず、勧請の年代詳ならず、寛保二年(1742)年に再興ありと云」と載るところから、少なくとも江戸中期までにはこの地に勧請されていたことがうかがわれる。本殿は古風な趣を持った一間社流づくりで、正面の御扉のほかに、左右の側面にも扉のついた珍しい構造を特徴としている。寛保二年の再興後、再建や大きな修復についての記録はないため、現存する社殿は、恐らくその際に建設されたものと思われる。 |
| ④ 長久寺 | |
 |
長久寺は天王山自性院と号する天台宗のお寺です。天台宗泉福寺(現:桶川市川田谷)の末寺で、もと庵室でしたが、慶安年中(1648~1652)に一寺になりました。本尊は不道明王です。不道明王を安置しているお寺院は市内に幾つかありますが、本尊としているのは、遍照院(真言宗)と長久寺の二ケ寺だけです。本尊の不道明王は、木造立像で、高さ68cmです。不道明王は忿怒相で表願され焚き清めて、衆生を守る仏様です。不動明王は五大明王の中心で最高の立場の明王です。賢者(使者)として、コンガラとセイタカの2童子が両脇についている、三尊形式です。この形式は、市内では、原市の「宝蔵寺」(真言宗)以外には有りません。 |
| ⑤ 原市大通り | |
 |
原市の市は室町時代後半に始まり、江戸時代には三・八の市と呼ばれ、月6度の市がたち、当時家並みは200件を超え相当な賑わいでした。通りに面した家では「庭」と呼ばれる広場があり、1軒1軒 間口は狭いが奥行きはとても長くなっています。今でも田中屋酒店、三角家、矢部家、星野家などに当時の面影が見られます。 |
| ⑥ 寶蔵寺・らかんまき | |
 |
宝蔵寺は、医王山と号する新義真言宗の寺院です。らかんまき(市指定文化財)は、樹齢500~600年、幹周り2.4m、高さ10m、九州南部・南西諸島に自生する槙科の常緑喬木です。毎年5月頃開花し秋に実を付け、その種子は青緑色の楕円形で、その基部に紅色の皮がついています。形が羅漢の姿に似ているので、”らかんまき”と呼ばれています。 らかんまき(羅漢槇)の実 |
| ⑦ 稲荷神社 | |
 |
主祭神は五穀を司る保食神(ウケモチノカミ)、慶長年間(1596~1615)に創祠されました。社殿左手に庚申塔(市指定文化財)があり「ここからさってみち」と書かれていて、原市と幸手がつながっていたことが伺えます。昭和56年(1981)新幹線開通に伴い、5mほど動かして現在地に移転しました。 |
| 終点 ニューシャトル沼南駅 | |
 |
ニューシャトル沼南駅です。トイレ・売店があります。また、駅前広場にはベンチが設置されていますので、小休止ができます。 |
<オプション観光スポット>
| (P1) 放光院 | |
 |
放光院は新義真言宗の寺院で、安養山と号し、開山の教養(きょうよう)上人(しょうにん)は慶長19(1614)年に没しているので、江戸時代初めの草創ということになります。(『新編武蔵風土記稿』より)『寺院・堂庵明細帳』では、元禄13(1700)年開基と記されていますが、放光院を菩提寺(ぼだいじ)にしている旗本松下氏の初代房利(ふさとし)は延宝4(1676)年8月に没し、この寺院に葬られています。松下房利は通称彦兵衛(ひこべえ)、御小姓(おこしょう)組の番士(ばんし)で、寛永10(1633)年2月に上尾下村・門前村・須カ谷村などで400石の領地を与えられています。松下氏が放光院を菩提寺にした年は不明ですが、所領の拝領年や初代房利の没年からみて、放光院の草創は元禄13年ではなく、江戸時代初期であったとみられます。 |